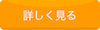医学部学士編入制度で医学部の夢に再チャレンジ!予備校の選び方

医学部に編入して、新たな道を切り開きたい方は学士編入制度で編入するという方法があります。
現役では医学部に進まなかった方、文系だった方、一度社会に出た方なども、様々な経験を生かして医学部に再チャレンジできます。
ただし、一般入試とは異なる編入制度で合格するためには、戦略的に対策をする必要があります。
強い意志や努力はもちろん、情報や実績が豊富な医学部予備校を活用し、医学部入学のチャンスを掴みましょう。
目次
学士編入制度とは?
学士編入制度は現役で医学部に進学しなかったものの、医学部に再チャレンジしたい方が利用できる制度です。
合格すれば、医学部に編入することが可能です。
例えば、現役時代の大学入試でも医学部を目指してはいたものの諦めてしまったが、やはり医学部に進みたいと考えている人が利用できます。
また、他の学部の大学へ入学、卒業したけれど、その後社会人になってから医学部への道に興味、関心が出てきた方も受験可能です。
学士編入制度を利用できる人
学士編入制度は、浪人して再受験するものとは異なります。
4年生大学に入学し、卒業した方や卒業見込みの方が利用できる制度で元々の大学の専攻学部はなんでも構いません。
そして、医学部に編入するという形になり、一般教養などの授業は省き専門課程に編入することが可能です。
大学を卒業し、社会人経験がある方にもチャンスがありますし、大学在学中の方も受験可能です。
いずれにしても、医学部入学への高い志、意欲を持っていることが必須となります。
それほど強い意志を持った上で、しっかりと受験対策をしなければ合格することは難しいです。
学士編入制度で入学する注意点
学士編入制度で医学部に入る場合は、2年次後期か3年次に編入することになります。
医学部といっても、1、2年次での授業は一般教養の授業も多いからです。
しかし、基礎医学、解剖学など、1〜2年次で医学に関連する授業の履修が設定されている大学の場合は、それらが入学後に受講できない可能性があります。
基礎医学や解剖学などは今後の医学部の勉強、医者として働くために重要なものです。
学士編入制度の利用を考えているなら、受験対策とともにこれらの基礎的な医学の勉強を自身で行っておく必要があります。
一般教養も含め、基礎からしっかり学んでいきたいのなら編入ではなく再受験として一般試験で入学を目指すべきでしょう。
学士編入制度の試験内容
学士編入制度ではどんな試験が行われているのでしょうか。
試験内容の特徴、一般入試との違いについて具体的にお伝えします。
学士編入制度の特徴
試験科目が少ない
医学部入試というと、科目数が多く受験が大変だというイメージがあるでしょう。
しかし、学士編入制度の場合は、科目としては英語と生命科学が基本です。
生命科学は基礎医学である生理学、解剖学、免疫学、生化学、分子生物学などがあり、試験対策のためだけの勉強ではなく、編入後に他の一般生と肩を並べて学んでいくために必須の内容です。
そして、将来医師として働いてくための基本的な知識を身につけるものであることから、前向きにモチベーションを持って学んでいけるでしょう。
試験対策を通して、狭い範囲を深く学ぶことができます。
英語に関しても、医師にとっては必須のものです。
海外の研究論文を読んだり、自身が論文を執筆したりすることも今後出てきます。
試験対策としては、英語で書かれた医学部関連の話題に触れ慣れていくことが重要です。
新聞記事やニュース、ドキュメンタリーなど英語で医学の情報を入れるように習慣づけていきましょう。
また、大学によっては数学の試験が必要なところもあります。
試験日程や合格の基準などが特殊
学士編入制度の試験は特殊です。
試験日程や合格の基準など大学ごとに異なるので十分にリサーチし、受験対策を行わなければなりません。
ペーパー試験の点数だけではなく、社会人経験、面接試験(個人、集団)、小論文試験などを合わせて総合的に判断されます。
国公立医学部への編入も可能
一般入試では国公立の医学部は非常に倍率が高く、狭き門となっています。
私立大学の医学部と比較して、学費を抑えられるからです。
難関国公立医学にも、学士編入制度を使って編入する方がおられ、現役時代には泣く泣く諦めてしまった方も、この制度を使って再チャレンジしています。
一般入試とは異なり、国公立大学を複数校受験することも可能です。
学士編入制度と一般入試の違い
試験スケジュール
学士編入制度を利用する方は、これまでに一般入試を経験してきた方なので、一般入試の感覚で受験スケジュールを考えていると失敗してしまいます。
まずは、学士編入制度のスケジュールをおさえた上で対策を始めましょう。
国公立大の学士編入制度の試験は、春から夏に出願し、8月から9月に1次試験と2次試験を受験します。
その後、9月に合格発表という流れです。
私立大の学士編入制度の試験は、秋頃に出願し、10月から12月に試験を行い、年内には合格発表となります。
一般入試だと私立大学の受験が先で、本命である国立大の受験が後になるというイメージでしょう。
一般入試は年明けに1次試験、2次試験があり、その後合格が決まります。
そのため、学士編入制度は一般入試より早い時期の受験になりますし、国公立と私立のスケジュールが反対になっています。
学士編入制度に対する各大学の対応は異なり、出願、試験のスケジュールや入学時期などが変更になるケースもあります。
こまめにリサーチし、最新の情報を得る必要があります。
受験戦略を決めるのが難しい
学士編入制度では大学ごとに試験科目などが異なり、しっかり情報収集し対策をするのが難しくなっています。
試験日が重ならなければ、複数の国公立大学の試験の受験も可能ですが、第一志望を決めるのはもちろんのこと 併願校の決め方も難しいです。
先述した通り、大学ごとに試験内容が違うので併願校を組むのに一苦労するほか、ただ勉強するだけでなく戦略が非常に大切になってくる試験です。
定員が少ない上、受験者は一般入試と異なり文系で学んできた方でも受験が可能だという点もその理由です。
この制度を利用して医学部に入学を希望する方は多く、競争率が高くなっているからです。
試験科目が少ないからといって、簡単だというわけでは決してなく、レベルの高い戦いになります。
学士編入制度での合格には医学部予備校がおすすめ!
特殊な試験のため、チャンス掴むためには努力だけでなく戦略的な対策が必要になります。
効率よく対策し合格を掴みたいなら、医学部予備校への通学がおすすめです。
医学部の情報が豊富で、試験攻略を専門的に行っている医学部予備校を活用していきましょう。
学士編入制度の対策ができる
医学部予備校では一般入試の対策だけでなく、学士編入制度の対策もできる予備校があります。
集団授業の場合は学士編入制度のコースがあるところを選びましょう。
もしくは、個人授業で学士編入制度に対応した指導ができるところで、マンツーマンで効率よく学んでいくのがおすすめです。
生命科学という科目は一般受験にはない科目なので、医学部予備校でも一般入試のカリキュラムに設定されていません。
学士編入制度での入学を目指していることを伝え、その対策のためのカリキュラムやコースがある予備校を選びましょう。
また、マンツーマンの個別指導を行っている予備校の場合も、学士編入制度での入学対策、指導ができる講師、テキストなどが準備されているかをチェックしておきましょう。
マンツーマンだと自分に必要な対策ができますが、一般入試向けの指導のみ対応の場合、マンツーマンでも意味がありません。
過去の合格実績からも、学士編入制度の合格実績、情報などが豊富で、対策が可能な予備校であるのかを判断できます。
医学部受験の情報やノウハウが豊富
学士編入制度でも試験対策には、情報収集が重要です。
大学ごとに傾向や内容が異なるため、一般入試以上に戦略的な対策が必要になってきます。
全国の各医学部の学士編入制度について、個人でリサーチ、分析するのは効率が悪いです。
医学部受験の情報が豊富で、試験攻略が得意なプロ集団である医学部予備校の活用が必須です。
また、医学部予備校は医学部受験に関して、様々な対策を練ります。
一般入試はもちろん、浪人しての再受験、学士編入制度での編入など医学部に入学するための方法は様々ですが、医学部予備校ではあらゆる対策をとっています。
そのため、学士編入制度での受験合格を目指しつつ一般入試での再入学など、他の道を模索、対策することも可能です。
医学部予備校の講師やアドバイザーなどが親身になって相談に乗り、進路指導を行ってくれます。
試験対策をしていく上で悩んでしまった時にも、頼れるプロがいるのは心強いでしょう。
学士編入制度で医学部に挑戦!おすすめの医学部予備校
学士編入制度での医学部入学にチャレンジする方におすすめの医学部予備校を3つピックアップしました。
それぞれの特徴をお伝えしますので、自分にとって最適の場を見つけてください。
医進の会
医進の会は、医学部再受験、学士編入制度の対策も行える医学部予備校です。
編入試験の対策経験も豊富で、しっかりとサポートしてもらえます。
学士編入制度を受験する人それぞれのケースに対応し、その人に合った方法で戦略的に受験対策ができます。
編入試験はもちろん、再受験という方法での対策を取ることも可能です。
いずれにしても、その人にとって最適な方法で医学部受験に導いてくれます。
1対1の個別指導なので、必要なことを徹底的に学べるシステムになっています。
必要なことを効率よく対策できるように、一人一人がオリジナルのテキスト、カリキュラムを使用することになっています。
テキストは講師のオリジナルのものもあります。
受講のコマ数なども自由に決められ、社会人や大学在学中の方が自分のスケジュールや予算などに合わせて対策できるので嬉しい要素です。
教室での授業はもちろん、オンラインでのリアルタイム、双方向授業も可能です。
強い意志を持ち、医学部編入を目指す方の強い味方になってくれます。
講師陣からの手厚いサポートがあるため受講者の満足度が高く、個別指導でもリーズナブルな学費であることも魅力です。
メディカルラボ
メディカルラボの授業は、「講義(学ぶ)→演習(試す)→講義(習得する)」という3ステップで、しっかりと学びが定着できるサイクルを作っているのが特徴です。
校舎での個別指導とオンライン授業の二つの方法があり、希望する方法で受講できます。
教室に関しては全国に校舎があり、そのネットワークを活用してどこにいても全国の医学部受験対策がとれます。
それぞれ希望の情報をもとに、一人一人の目標を立て、それに沿ったカリキュラムやテキストを利用して個別指導を行っています。
テキストは市販のものを使用しています。
現役医大生のチューターが在籍しており、質問対応をしてくれます。
この質問対応に関しても、教室だけでなくオンラインでも対応します。
些細な疑問をそのままにせずに、安心して次に進めます。
日々の勉強については、個別担任がついてサポートをします。
定期的に面談があるので、ペースメーカーとなり、計画的な学びをフォローしてくれるでしょう。
メルリックス学院
メルリックス学院は特に、私立医学部、歯学部の受験に強い医学部予備校です。
国公立医学部ではなく、私立医学部を志望している方におすすめです。
面接、小論文の対策に力を入れているので各医学部の対策が十分に行え、編入試験にも対応しています。
授業は、集団授業、個別指導、オンラインなどのコースから選べて講師は医学部、歯学部受験のプロ、学生講師はいません。
オンラインでも一対一の双方向での授業なので、対面と遜色なく指導が受けられます。
オンラインコースは決まったカリキュラムがないので、希望の回数、時間で個人に合った対策ができます。
普段はオンラインで受講し、休暇期間のみ東京、大阪、名古屋の校舎で授業を受けることも可能です。
臨機応変に対応できるのがメリットで校舎での集団授業と個別指導に関しても、どちらか一方を受講したり、併用したりすることが可能です。