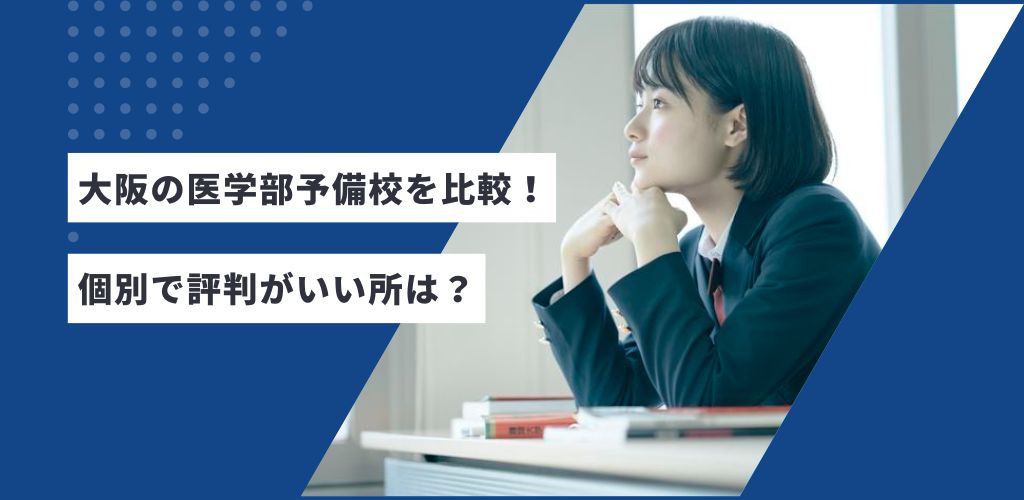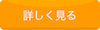医者になるには医学部入学から何年かかる?

医者になるという高い目標を持ち、医学部受験を目指しているものの、医者になるまでの道のりは決して簡単なものではありません。
医学部入学が叶ったとして、それから一人前になるまで何年もかかります。
そこで、医学部合格をしてから、どのような流れで勉強、研修などを進めていくのか、医者になれるまでに何年かかるのかをまとめました。
時間がかかってしまうケースもお伝えするので、まずは最短で医学部合格を目指していきましょう。
目次
医学部合格〜医者になるまでの流れ
医学部は最難関学部の一つであるため、そこをゴールとして必死に勉強している受験生は多くいらっしゃることでしょう。
しかし、医学部合格は医者になるためのスタートラインに立ったに過ぎません。
そこからが医者になるためのさらに険しい道のりとなっていくのです。
そこで、医学部入学から、医者になるまでの流れについて簡単にご紹介します。
将来の自分をシミュレーションしながらご覧ください。
医学部生として知識を身につける
多くの大学は4年制ですが、医学部、歯学部、薬学部の場合は6年間大学で学ばなければなりません。
この6年間で、医学に関する基本的な知識を学びます。
そして、医学部に合格すると一つの山を乗り越えて、開放的な気分になるかもしれませんが、入学後もしっかりと勉学に打ち込み続ける必要があるのです。
座学で知識をつけ、臨床実習として現場で学び、身につけていきます。
卒業するまでには、多くの試験、実習をクリアしていかなければならなりません。
医師国家資格の取得
例年、卒業前の2月に実施されている医師国家試験に合格する必要があります。
医学部卒業か卒業見込みの方が対象となり、卒業試験と共に合格しなければ6年の医学部生活を過ごしても、次のステップに進むことができません。
単位を落としているなどで留年することが決まっていると、受験すらできませんので、医師国家試験を受験する年の過ごし方は非常に重要です。
研修医として勤務
医学部を卒業し、医師国家資格を取得しても、まだ一人前の医者ではなく、卒業後に研修医になります。
初期研修期間、後期研修期間の2つに進む必要があります。
初期臨床研修の期間は2年で、その後に医者になる人もいます。
しかし、ほとんどは3年間ある後期臨床研修まで進み、その後に医者になります。
つまり、研修医として働くのはほとんどの場合で5年だということです。
医者になるまで最低何年かかる?
医学部入学から医者になるまでの期間と流れについて、具体的にご説明します。
最低で何年かかるのか、その間にどんなことをしていくのか、想像しながら見ていきましょう。
医学部生として6年間
医学部として学ぶ6年は、年数だけを見ると長く感じてしまうかもしれません。
しかし、実際にはカリキュラムが詰まった、濃い6年です。
どの医学部でも6年間を大きく分けると、2年ごとに3つのタームになります。
そのステップを踏んで、着実に知識や経験をつけていくので、長いようで短くもある6年間なのです。
1〜2年は基礎、3〜4年は臨床、5〜6年は実習です。
基礎
正常な人体の構造や機能について学びます。
医者として、異常を察知し、適切な判断をするためにも、正常な状態とはどんなものであるのかを知る必要があるからです。
具体的には解剖、免疫、生化学(代謝学)などを学んでいきます。
臨床
異常、簡単に言うと病気について学習します。
異常が起こる原因別に「部位別」「時期別」「機能別」に学んでいくのです。
「部位別」では、脳に異常がある場合は脳神経科目というように、体に異常が出ている場所で分けて知識をつけていきます。
「時期別」では、小さいお子さんを対象とした小児科、妊娠・出産期を中心とした年代の女性を対象とした産婦人科というように、ライフステージで特定の病気や異常が出やすい時期ごとに医学知識を深めていきます。
「機能別」は体が異常を起こした原因によって分けられます。
例えば、細菌の侵入による病気は感染症科目、体力や防御力が落ちたことによる病気は免疫・アレルギー科目のように分けられます。
実習
これまで大学で座学を中心として学んだことについて、現場の実際の患者様から学ばせてもらいます。
最近は5年生になる前、4年生の1月に実習が始まっています。
実際に現場で見て、触れて、経験として身をもって学んでいく段階です。
実習とはいえ、実際に来院した患者様の診察を行うため、患者様の不安を極力なくすことが必要となります。
そのため、最低限の知識があるかを測る「CBT」テスト、最低限の技術があるかを測る「OSCE」テストに合格しなければ実習に参加できないのです。
初期臨床研修2年→最短8年で医者に!
国家試験に合格し、医師免許を取得すればすぐに医者として勤務できるわけではありません。
その後に、初期臨床研修が2年あります。
「研修医」として、いろいろな診療科をローテーションで回り、それぞれの基礎知識を現場で身につける期間です。
この期間は、他のアルバイトなども認められていないので、しっかりと研修だけに集中し、医者として働く第一歩となります。
初期臨床研修は、大学病院や厚生労働大臣が認定した医療機関で研修が行われます。
配属先は医師臨床マッチングというシステムにより決定されるため、自分で自由に選べるわけではありません。
いろいろな診療科を回りますが、内科、救急部門、地域医療は必修です。
必修以外にも、外科、麻酔科、小児科、産婦人科、精神科の中から、選択した2つの診療科を回ります。
様々な診療科を回ることで、医療の知識、見識を広げること、自分が目指す診療科を決定することに繋がります。
また、プライマリケアに最も重点が置かれており、医者としても資質、人格を形成する役割も持っています。
この初期臨床研修の後、保険医として登録し、開業することが可能です。
また、勤務医として医者になることもできます。
つまり、18歳で医学部現役合格すれば、最短8年、26歳で医者になれるということです。
ただし、実際にはさらに研修を続けるのが一般的となっています。
後期臨床研修3年→一般的には11年で医者に!
2年間の初期臨床研修が終わると、後期臨床研修に進むのが一般的です。
この研修期間は3年で、各大学の医局か民間病院で研修を行っています。
初期臨床研修で自分に最も合っていると感じ、今後も携わっていきたい診療科を選択し、そこで「専攻医」として研修を続けていきます。
認定医や専門医を目指して研修を受ける、いわば、医者の卵のようなものです。
より専門的な知識をつけ、医療現場で学びながら勤務します。
専門知識を深め、経験を積むことももちろんのことですが、患者様やそのご家族と良好な関係を築くことも身をもって学んでいくのです。
また、他のアルバイトや外勤なども認められているので、ダブルワークをしている方もいます。
18歳で医学部現役合格すれば、後期臨床研修が終わるまで11年かかるので、独り立ちは29歳。
初期臨床研修の後に医師として活躍はできますが、後期臨床研修を受けるほうが即戦力を期待する病院からの需要が高まる傾向にあり、就職後の給料面でも有利となります。
医者になるまでに時間がかかるケース
最短で8年、一般的には11年、医学部入学から医者になるまでかかることがわかりました。
しかし、最難関の医学部での学びは決してたやすいものではなく、様々な事情によりさらに時間がかかるケースもあります。
医者になるまでに、年数がかかってしまうケースはどんな場合でしょうか。
医学部受験で浪人するケース
医学部志望者が現役合格できるのは約3分の1。
1浪して合格している方が約3分の1、残り3分の1は2浪以上してから合格した方が占めています。
したがって、ストレートで医学部入学することは簡単ではないことがわかります。
医学部志望者は、こうした現実があることを理解した上で、現役合格できる3分の1に入るのだという強い意志を持って、受験対策をしていきましょう。
医学部で留年するケース
医学部生の10〜16%ほどは様々な理由で留年しています。
他の学部よりも進級条件が難しいため、単位を1つでも落とすと進級ができない場合があります。
単位取得条件として、テストや出席率などの基準が厳しく設定されているためです。
医学部入学後にモチベーションを保てずに苦労する方も少なくはありません。
医学部合格がゴールになってしまっていて、入学後に燃え尽きてモチベーションが下がってしまう学生もいます。
また、医学部以外の比較的単位取得が厳しくない学部の友人、サークルやバイトなどでの人間関係、入学後の一人暮らし、など大学生活で周りの誘惑に負けて、勉強に集中できずに留年する人もいるでしょう。
また、こうした大学生活での環境の変化は、新たな夢や目標を持つきっかけともなり得ます。
留学などの他のやりたいことを優先し、医学部を卒業するのが遅れてしまうこともあるかもしれません。
国家資格に不合格するケース
6年間の医学部生活が終わると、卒業試験と国家試験があります。
それらを一発合格できずに、不合格を繰り返すとその分医者になるまでに年数がかかってしまいます。
国家試験に合格しなければ、研修医の段階に進むことはできません。
医師国家試験の合格基準は、年によっても変化しますが、必修80%以上、一般臨床65%〜70%以上、禁忌肢3問以下となっています。
必修は6年間真面目に勉強していれば解けるであろう、簡単な問題です。
一般臨床は、患者様の状態が設定されており、どんな診断、処置、検査をすべきかを問う実践的な問題です。
さらに、問題の中には、禁忌肢といって絶対に間違えてはならない、現場では患者の生死に関わるような選択肢が紛れています。
合格基準が3問以下の場合、4問以上選んでしまうと他の正答率が高くても不合格になってしまいます。
以上の基準をもとに、例年国家試験の合格率は90%以上です。
非常に高いと言えますが、一方で、医師を目指して必死に学んでいても10%程は不合格という結果になってしまうのです。
プレッシャーもかかる一発勝負の試験なので、試験日までの勉強はもちろんのこと、体調や精神面でのコンディションも保っていく必要があります。
できるだけ早く医学部生になるには?
医学部に入学してからも、医者として働き始めるまでには長い道のりを一つ一つクリアしていかなければなりません。
いち早く医者として活躍するためにも、まずは医学部一発合格を目指していきましょう!
現役合格を目指す
医者としての勉強をできるだけ早くスタートさせるためには、まずは医学部現役合格を目指しましょう。
現役生の場合は特に、難関だから浪人も覚悟の上で…と弱気になって勉強するのではなく、必ず医学部現役合格するのだという気持ちで努力していきましょう。
医学部合格には、学力はもちろんのこと、戦略も非常に重要です。
医学部を目指す場合は、進学校に通っている方であっても、並行して学ぶ塾として、医学部専門予備校を選ぶ方が多いです。
現役生の場合は、放課後の時間帯や土日に集団授業や個別指導などのカリキュラムを設定するため忙しくなりがち。
効率よく学ぶためには早期に志望校を設定し、個別指導で学んでいくのがおすすめといえるでしょう。
個別指導を行っている大阪の医学部予備校では「医進の会」などがあります。
普段通う高校では、医学部志望の同級生があまりおらず、不安になっている方もいらっしゃるでしょう。
医学部予備校では、これまでの合格実績、豊富な情報などから、医学部合格を現実的に考えて対策をしていけます。
医進の会など、大阪の医学部予備校についてはこちらをご覧ください。
現役生に限らず医学部専門予備校を活用しよう
現役合格を目指していたものの、やはり難関である医学部は、多浪生も多いです。
浪人生活は時間があると思われがちですが、モチベーションを保ちつつ、しっかりと効率よく学んでいくのは簡単ではありません。
浪人生であれば、なおさら医学部専門予備校を活用していくことがおすすめです。
医学部専門予備校では、現役合格を目指す高校生コースよりも、浪人生、社会人経験者向け(医学部編入制度利用)のコースなどが充実しているところもあるので、自分に合ったコースでしっかり学べます。
マンツーマン指導であっても、現役生と浪人生では学び方、対策の仕方が違います。
その人に合った方法でサポートしてもらえるのが医学部予備校の強みです。
また、医学部志望者の中には、他の学部で学んでいる方、一度社会人として働いた方もいらっしゃるでしょう。
人生経験を積んだ上で、医学部を目指すようになることは珍しくはありません。
そのような方は、医学部編入制度を利用すれば、医学部の2年次もしくは3年次から編入できる可能性があります。
年齢を重ねており、いち早く医者になりたいと思っている方が、医者になるまでの期間を短くすることができます。
医学部編入制度は、特別な入試方法であるため、情報や戦略がさらに重要になってきます。
医学部専門予備校の力を借りて、合格対策をしていきましょう。
学士編入制度についてはこちらで詳しく解説しています。